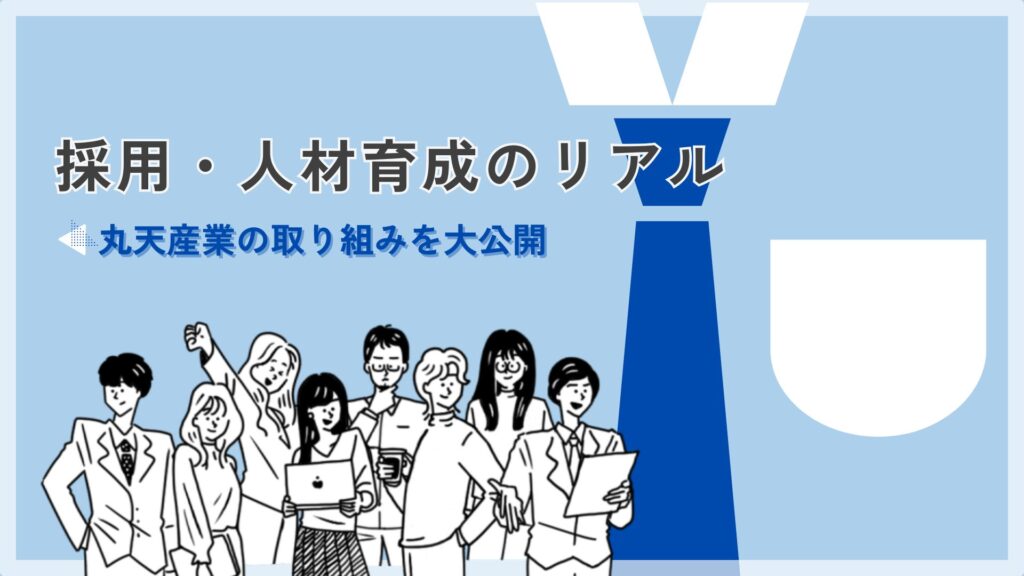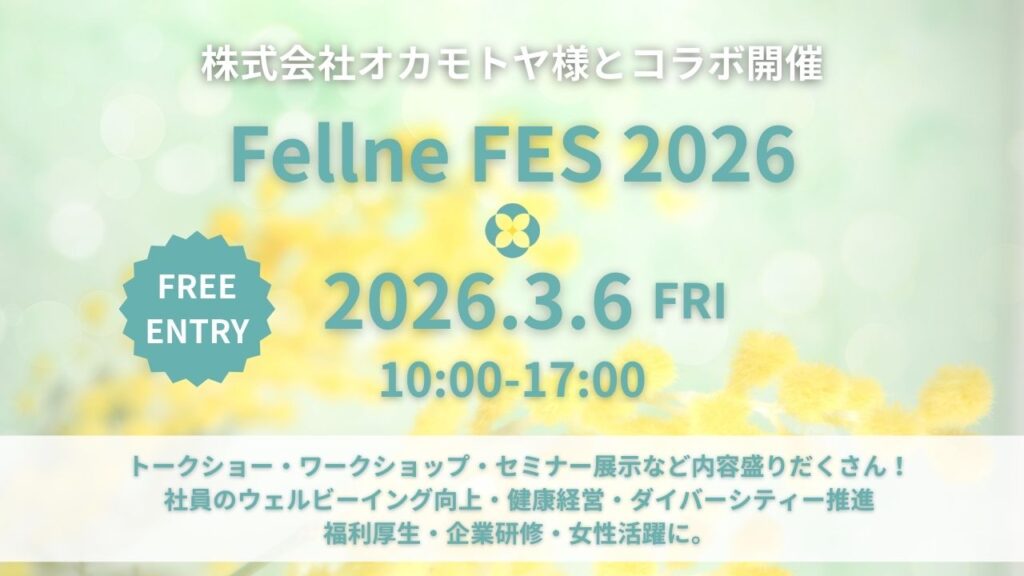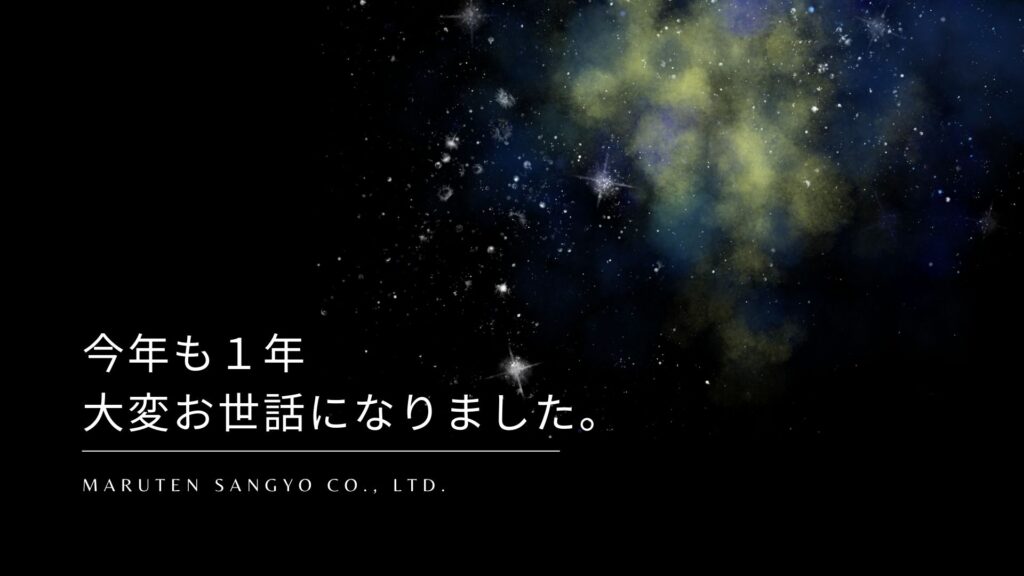あっという間に5月になりました・・・。
4月に迎えた新入社員が少しずつ職場に馴染んできた頃。
ちょうど同じ時期に、来年に向けた採用活動も本格的に始まる——。
そんな“二つの時間軸”を並行して動かさなければならないのが、人事担当者のリアルかもしれません。
私たち丸天産業でも、この時期は「社内で育てること」と「新たな出会いをつくること」の両方に取り組む、いわば“人の季節”です。
目次
はじめに
現在多くの企業が直面している採用難、人材の早期離職、育成スピードの低下。
「なかなか応募が来ない」
「採用できてもすぐに退職してしまう」
「育て方が難しい」
などなど・・・
そんなお悩みを抱えている人事担当の方も多いのではないでしょうか。
私たち丸天産業も例外ではございません。
そこで今回は、弊社が行っている採用から育成までのリアルな取り組みを、入社3年目になる企画室社員の私から皆様へご紹介してみたいと思います。
向き合ってきた課題
弊社は働き方・働く空間のデザインを事業の柱としています。
オフィス設計や空間デザインを通じて、より良い働き方を提案する一方で、採用・人材定着についての課題もありました。
例えば・・
- 新入社員を採用しても、仕事内容や社風とのミスマッチで早期離職してしまう
- 「お客様のために働く」という価値観が強く、結果として残業が慢性化
- 研修や面談などが整備されておらず、キャリアを描けない
こうした課題と向き合い、弊社は試行錯誤しながら人事戦略の見直しを行いました。
リアルな取り組み —出会いの場を増やす
①学生さんとの接点を増やす
まず着手したのが、学生さんとの接点を増やすこと。
採用の第一歩として、就職ポータルサイト「マイナビ」を活用し募集情報と問い合わせ先を明確にすることで、応募へのステップに進みやすくしました。
他にも学生さんとつながるきっかけづくりとして、学生交流会の実施、大学生向けセミナーへの登壇、インターンシップ受入れの拡充、SNSを活用した採用情報の見える化など、多方向から「丸天産業」について知っていただけるよう活動を広げてまいりました。

とはいえ、広く募集すればするほど良いとも限らず、採用の段階でミスマッチを防ぐことにも重きを置かなければいけません。
そこで弊社は、自社の事業内容や社風をリアルに感じていただけるような機会を、敢えて増やすようにしています。
②さまざまなタイプのインターンシップ
特にインターンシップでは、1day、5days、1ヶ月といった短期のものに加え、半年~1年間といった長期インターンシップの受け入れも積極的に行っています。
長期インターンシップでは、より社員の業務内容に近しいお仕事に関わっていただくことで、丸天産業で働くイメージを具体的に持つことができ、「自身のキャリアプランを描けた」「やりたいことにマッチしていた」などの理由から入社を希望していただけるケースもあります。
また、希望される学生さんには忘年会やお餅つき、部活動など会社の行事ごとにも参加してもらったりと、社員と和気あいあいとコミュニケーションをとれるきっかけを多く提供しています。

今年入社してくれた新入社員の中には、インターンシップへの参加が応募のきっかけになった方も^^
ということで、インターン生から今年入社してくれたSさんに、ちょっぴりインタビューしてみました!
——丸天産業に入社したいと思った理由は?——

新入社員Sさん
インターンシップで描けた、”理想の働き方”
求人サイトでインターンシップを探していたら、丸天産業の募集を見つけました。
1dayインターンで訪問したところ、オフィスの綺麗さに衝撃を受け、フリーアドレスの導入など働き方の自由度も高く、「ここで働きたい!」と思い、自ら5daysへの参加を希望しました。
社員さんがたくさん声をかけてくださり、社内の会話も活発で、そのアットホームな雰囲気にも惹かれ入社を希望しました。
インターンシップを通して、理想の働き方とのマッチ度を実感してもらえるメリットもあるようです。
ちなみに私が初めて訪問した時は新社屋建設中のため仮事務所でしたので、これから新しい社屋で働けるのを想像しワクワクドキドキしていました♪
③SNS
弊社で運用しているInstagramは今期から採用向けに切り替え、自社の雰囲気がわかるような発信内容にすることで、学生とのマッチング精度の向上を図っています。
また、なんといってもZ世代はSNSの匠。今の時代はSNSで企業をリサーチし、ダイレクトメッセージから問い合わせをする・・・なんていう時代になりつつあります。SNSを見ていたら偶然弊社の投稿を目にしてもらえて、気になって申し込み!といった期待も込めて発信を継続しています。

▼採用に向けた動画をSNSで発信
私たちと一緒に働きませんか?
ちなみに弊社では、長期インターンシップとして来てくれている学生さんと連携しながらSNSの企画・運営を行っております。さすがは大学生・・・!流行に詳しく学生目線の意見などもくれるので、私たちの方が学ばせてもらうことも多々あります。
▼具体的な取り組みについてもご紹介しています

リアルな取り組み —定着率を上げるためのフォローアップ体制
せっかく採用できても、早期離職してしまう・・・といった悲しい事例も過去にはありました。
どこに問題があるのか?原因を検討したところ、下記のようなことが考えられました。
- 入社してもらうことが目的になってしまい、入社後にミスマッチが明らかになる
- 社内のサポート体制が不十分
- この会社で自分はどう成長していけるのか、キャリアが描けないことによる不安
弊社ではこうした課題に対し、新入社員が安心して成長していける環境に整えるところから始めました。
①研修期間のフォローアップ体制
4カ月間の研修期間を終えた後、本人と面談を重ねながら配属先を決めていきます。まずは自社のこと、そして各部署の業務を知ってもらい、時には体験してもらうことで、自社理解を深めています。そういった過程を経て、強みが最大限に活かされキャリアプランに合う部署がどこなのか、本人の意向も踏まえてじっくりと会話しながら配属部署を決めていきます。
②エルダー制度で、身近な先輩が全力サポート
弊社は、比較的年齢が近い先輩社員が教育係となって1対1で新入社員のサポートを行う「エルダー制度」を採用しています。エルダー(先輩社員)は実務の指導だけでなく、新入社員の精神面のサポートからちょっとした相談にも乗ってくれる身近な存在として、新入社員の不安を取り除きます。
人事担当者や上司・エルダーだけでなく、社員全員で新入社員をフォローする。そんな取組です^^
この時期に多いと言われる“5月病”
新入社員とどう関わる?
新年度がスタートして1ヶ月。
学生と社会人とのギャップを肌で感じながら頑張っている新入社員にとっても、迎えた側の先輩社員にとっても、どういった声をかけたらいいか、距離感が難しいと感じやすいタイミングではないでしょうか。
「成長してるはずなのに、なんだか不安そう」
「1ヶ月経って、ちょっと疲れが出てきているかも…?」
そんなときは、いったん“教える”をやめて、“問いかけてみる”のもひとつの手です。
- 「ここまでの研修どうだった?」
- 「何か気になることある?」
- 「週末はリフレッシュできてる?」
正解を求めるよりも、ただ話を聴く時間が、新たな信頼や気づきにつながるかもしれません。
私も社会人になりたての時は右も左も分からず、常に緊張した状態でしたが、見かけると声をかけてくださり、時にはお仕事以外の話で緊張をほぐしてくださる先輩方の温かさに救われました。
先輩・上司からの何気ない声掛けが、新入社員にとって一番の励みだったりします^^
おわりに
いかがでしたでしょうか。
入社当時、世代・部署を超えた社員が集まる打ち合わせに参加した際、若手が前のめりで活発に発言し、それに対して先輩社員が「それめっちゃいいね!」と賛同していました。その光景を見て、「経験の浅い社員の意見もこんなに受け入れてもらえるんだ!」と衝撃を受けた日のことを、今でもよく覚えています。どんな立場であれ、まずは思いを傾聴し、相手を理解するという風土づくりが、若手のチカラを最大限に発揮させ、互いの成長につながるのではないかと感じます。
せっかくのご縁で入社してくれた社員が、安心して力を伸ばしていけるように——
人事だけでなく、社員一人ひとりが新入社員と関わる取り組みを今後も継続し、社員みんなでチカラを合わせて一緒に成長していけるような組織づくりに尽力してまいります。